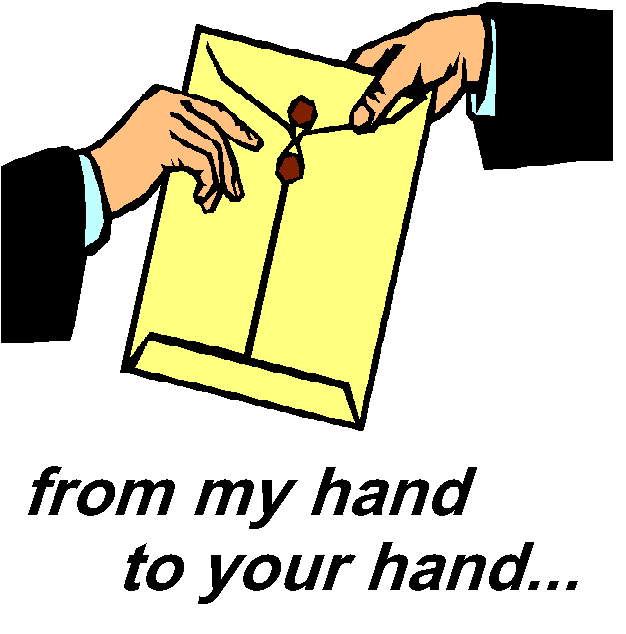認定NPO法人とは
認定NPO法人制度 とは、NPO法人への寄附を促すことにより、その活動を支援するために税制上設けられた措置で、NPO法人のうち一定の要件を満たすものについて、所轄庁が認定を行う制度です。従来は、国税庁が認定事務を管轄していましたが、2012年4月1日からは、都道府県知事又は政令指定都市の市長が所轄庁となりました。
認定NPO法人となるためには、次の(1)〜(9)の基準を満たす必要があります。
(1) パブリックサポートテスト(PST)に適合すること
(2) 共益的な活動の占める割合が50%未満であること
(3) 運営組織及び経理が適切であること
(4) 事業活動の内容が適切であること
(5) 情報公開を適切に行っていること
(6) 事業報告書等を所轄庁に提出していること
(7) 法令違反、不正の行為、公益に反する事実等がないこと
(8) 設立の日から1年を超える期間が経過していること
(9) 欠格事由に該当していないこと
ここでは、上の認定基準の全てを解説することは省略しますが、やはり一番重要なのは(1)のパブリックサポートテストです。 これは「広く市民からの支援を受けているかどうかを判断するための基準」ですが、具体的には、以下のような3つの基準があります。
(1) 相対値基準: 実績判定期間における経常収入金額のうちに寄附金等収入金額の占める割合が5分の1以上であること。
(2) 絶対値基準: 実績判定期間内の各事業年度中の寄附金の額の総額が3,000円以上である寄附者の数が、年平均100人以上であること。
(3) 条例個別指定: 認定NPO法人としての認定申請書の提出前日までに、事務所のある都道府県又は市区町村の条例により、個人住民税の寄附金税額控除の対象となる法人として個別に指定を受けていること。
このうち、やはり一番わかりやすいのは(2)の絶対値基準ですね。 と言うことで、3千円以上寄附してくれる人を1年間で100人以上集めることを目指して下さい。 大きな企業からの多額の寄附はないけれど、多くの支援者が少しずつ寄附してくれているような法人におすすめです。なお、どうしてもパブリックサポートテスト(PST)をクリアできない場合は、仮認定制度を利用することも可能です。
仮認定NPO法人 とは、2012年4月1日のNPO法改正によって、新たに設けられた制度です。設立されたばかりの法人は、寄附を十分に集めることができず、上述のパブリックサポートテスト(PST)をクリアできないことが多いです。そこで、その法人の運営組織や活動内容が適正であり、かつ公益活動を展開する基盤があると所轄庁が認めた場合には、"仮認定"NPO法人となることができ、認定NPO法人に近い税制優遇を受けることが可能となります。仮認定NPO法人は、パブリックサポートテスト(PST)をクリアする必要がありません。
仮認定NPO法人は、設立後間もない法人を対象としているため、原則として設立の日から5年を経過していない法人に限定されています。しかしながら、改正NPO法が施行された2012年4月1日から3年間は、設立の日から5年を既に経過してしまった法人も含めて全ての法人が、仮認定を申請することができます。
パブリックサポートテスト(PST)をクリアしなくても、"仮"とはいえ認定が受けられるのですから、これは申請しない手はないですよね。設立から5年以上が経過した法人も、今がチャンスです
!!
【認定NPO法人のメリット】
○ 寄附を集めやすくなる。
・個人が認定NPO法人に対し、特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合には、特定寄付金に該当し、寄附金控除(所得控除)又は税額控除のいずれかの控除を選択適用できる。
・法人が認定NPO法人に対し、特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合には、一般寄付金の損金算入限度額とは別に、特定公益増進法人に対する寄附金の額と合わせて、特別損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められる。
※要するに、NPO法人自体に対する税制優遇ではなく、認定NPO法人に寄附してくれた寄附者に対しても、税制優遇措置を施しましょう、という制度です。「いくらか税金が安くなるのならNPOに寄附してみよう」とか、「まるまる税金で持って行かれるくらいならこの法人のやっていることを応援しよう」と、いうような動機付けになります。
○ みなし寄附金制度を利用できる。
・認定NPO法人が、その収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業で特定非営利活動に係る事業に支出した金額は、その収益事業にかかる寄附金の額とみなされ、一定の範囲内で損金算入が認められます。
※要するに、収益事業を行うことによって上がった利益はそのままですと課税対象となりますが、これを特定非営利活動に係る事業の資金として支出した場合、寄附金とみなされて(=みなし寄附金)、損金算入が認められる、と言う制度です。
【認定NPO法人のデメリット】
○ NPO法人の要件に加えてさらに"認定"NPOのための要件を満たさなければならない。
・パブリックサポートテスト。 景気の動向によって寄附者の数は増減する。
・共益的な活動の事業費率にも制限があり、活動の自由度が下がる。
・要件が増えた分、行政のシバリがキツくなるし、事務作業が増える。
○ 有効期間に制限がある。
・認定NPO法人の有効期間は、認定の日から5年間。
・認定NPOの地位をを維持するためには更新手続を行わなければならない。
【こんな団体におすすめ】
○ 小口の寄附者が多数存在する団体。 大きな企業からの多額の寄附はないけれど、多くの支援者が少しずつ寄附してくれているような団体にはおすすめです。
○ 主な収益源を寄附に頼っている団体。 収益事業を行っておらず、法人運営のための原資を寄附金に頼っているような団体は、やはり寄附金を集めなければ話になりません。ならば、少しでも寄附を集め安くするために、寄附者側も税制優遇措置が受けられる認定NPO法人になるメリットはあるのではないでしょうか。
当事務所がお手伝いできること
当事務所では、認定NPO法人の活動について、以下のようなお手伝いが可能です。
○ 認定NPOになるための認定申請手続 (相談、書類作成、申請代行、審査中の折衝等)
○ 各種変更の届出手続
○ 議事録、事業計画、事業報告の作成
○ 会計記帳
○ 毎事業年度終了後の事業報告書、決算書類等の所轄庁への提出
○ 補助金・助成金等の申請
○ 業務委託に関する行政庁への申請、届出、報告等の手続
○ 介護事業、保育事業、その他の許認可申請手続
○ 法人の運営管理全般に関する相談、アドバイス